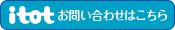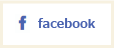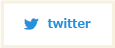「目白不動尊」から目白という地名が誕生
東京都豊島区の西部に広がる目白エリアはJR山手線「目白」駅周辺という地の利にもかかわらず、閑静な住宅街が広がり、古くから人気の住宅地です。

目白という地名は、江戸時代に江戸五色不動のひとつとして「金乗院」に「目白不動尊」が祀られるようになったことに由来しているといわれています。江戸五色不動は五行思想の五色(白・黒・赤・青・黄)にちなんだ不動尊を祀る寺で、都内には他にも「目黒不動尊」や「目黄不動尊」といった色の名前が付いた不動尊があります。
明治時代から「学習院大学」のキャンパスが立地

目白エリアのシンボル的存在となっている「学習院大学」はもともと公家の教育機関として京都に設けられた学習所をルーツとしたものです、1884(明治17)年からは官立学校に移行し、1908(明治41)年に現在の場所に移転しました。
戦後、1947(昭和22)年からは私立学校となり、現在も約18万ヘクタールの敷地を誇る「目白キャンパス」で約9000人の学生が学んでいます。この「目白キャンパス」内には豊かな緑の中に明治時代から大正時代にかけて建てられた校舎が今も残り、目白の街に落ち着きと潤いをもたらしています。
大正時代から邸宅街として発展
目白周辺は、江戸時代から武家屋敷が多く建てられていました。明治以降は、こうした武家屋敷の跡地を利用して近衛家や相馬家など旧華族の邸宅が設けられます。

その後、大正時代になると「目白」駅の西側、西武池袋線の線路の南側一帯で宅地開発が行われました。この一帯には住居付きアトリエも多く建てられ、画家や音楽家など多くの芸術家が暮らしていたといいます。近年は大正時代から昭和初期にこの地に花開いた文化を池袋モンパルナスと呼び再評価する動きがあり、「豊島区立熊谷守一美術館」や「アトリエ村資料室」などを訪ねれば、当時の面影を感じることができるでしょう。
目白の邸宅街としての地位を確立した「目白文化村」と「徳川ビレッジ」
大正時代末期には、目白通りの南側でも箱根土地株式会社により宅地開発が行われ、1922(大正11)年から「目白文化村」として販売が開始されています。関東大震災以降は被害が少なかった山手への移住が盛んになったことから「目白文化村」も人気を呼び、4回に分けて追加の分譲が行われました。
また、明治維新後、華族となった尾張徳川家は1930(昭和5)年に目白に邸宅を建て、この地で暮らすようになりました。こうした動きもあり、戦前までに目白は邸宅街としての地位を確立します。現在、尾張徳川家の本邸があった場所は「徳川ビレッジ」となり、駐日大使が暮らすなど都内を代表する邸宅街として知られるようになりました。また、「徳川ビレッジ」の一角には尾張徳川家が所蔵する美術品の管理を行う徳川黎明会の事務所があり、風格のある建物は目白の街並みに気品を与えています。
邸宅街としての歴史を受け継ぐ目白エリア。この街には今もほかの街にはない魅力があふれています。
都内有数の歴史を誇る邸宅街、目白
所在地:東京都豊島区