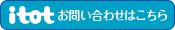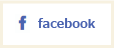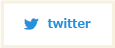東京23区の中央に位置する中央区日本橋は、江戸時代に五街道の起点とされ、古くから日本・東京の中心として発展してきました。現在もビジネスやショッピング拠点として重要な役割を担っています。こうした歴史を受け継ぎながらも、日本橋をさらに魅力ある街へ進化させようと2000年代から始まったのが「日本橋再生計画」です。

「日本橋再生計画」は「コレド日本橋」や「コレド室町」など新たなショッピング施設が誕生したほか、ビジネス拠点やコミュニティ拠点も整備され、第2ステージまでが完了しました。
「残しながら、蘇らせながら、創っていく」日本橋エリア
「日本橋再生計画」では「残しながら、蘇らせながら、創っていく」を開発コンセプトに掲げて推進しています。

これまでの第2ステージでは「産業創造」「界隈創生」「地域共生」「水都再生」の4つをキーワードに、ライフサイエンス領域の拠点整備、路地の維持・整備、コミュニティと協働したイベント開催など、ソフトとハードの融合による街づくりが行われてきました。具体的には、2014(平成26)年に「コレド室町2・3」がそれぞれ誕生したほか、2018(平成30)年には「日本橋髙島屋三井ビルディング」も完成しています。また、2014(平成26)年に「福徳神社」の社殿を再建したり、2016(平成28)には「福徳の森」を整備したりと地域のコミュニティにも様々な配慮を行っていることも特徴です。
計画は第3ステージへ
計画はこの「日本橋室町三井タワー」の完成をきっかけに第3ステージとなりました。第3ステージでは対象となるエリアを隅田川から日本橋川に挟まれた「GREATER日本橋」に広げ、第2ステージまでの開発コンセプトと4つのキーワードを引き継ぎつつ、より幅広い立場の組織や人を巻き込みながら、街づくりを進めていく予定です。
第3ステージの重点構想には「豊かな水辺の再生」「新たな産業の創造」「世界とつながる国際イベントの開催」の3つを掲げ、日本橋川沿いの親水空間整備、ライフサイエンス領域に比べ宇宙領域、モビリティ領域、食領域の拠点整備、街全体を会場とした国際的イベントの開催などが検討されています。
首都高速都心環状線の地下化も進む
三井グループが進める「日本橋再生計画」と合わせて注目されているのが、首都高速都心環状線の地下化計画です。首都高速道路は高度経済成長期の1964(昭和39)年に開催された東京オリンピックに合わせて建設されました。用地取得などを行う準備期間が短かった影響もあり、日本橋川の上に建設が行われた結果、街のシンボルでもある「日本橋」の上が覆われている状態になっています。

この日本橋川沿いの親水空間をより魅力あるものにするため、首都高速都心環状線「神田橋」JCTから「江戸橋」JCT間約1.2kmの地下化が都市計画決定されました。
「日本橋再生計画」の中でも、この首都高速都心環状線の地下化が考慮されており、日本橋川沿いに親水空間の整備・展開することで、開放的な景観が戻ることになります。
「東京」駅八重洲口前での3つの再開発が進行中

日本橋エリア周辺では、「東京」駅八重洲口周辺の再開発も活発化しています。「東京」駅八重洲口前では「八重洲一丁目東B地区」「八重洲二丁目北地区」「八重洲二丁目中地区」の3つの再開発が動き出しています。
「八重洲一丁目東B地区」では地上51階地下4階の高層ビルが、「八重洲二丁目北地区」では地上45階地下4階の高層ビルなど2棟が、「八重洲二丁目中地区」では地上46階地下4階の高層ビルが誕生し、それぞれオフィスやショッピング施設、住宅などが入ります。
これらの再開発では「羽田空港」や「成田空港」に向かうバスや地方都市への高速バスが発着する大規模バスターミナルの整備も行われるほか、「東京」駅から再開発エリアを経て、周辺エリアにつながる歩行者ネットワークも設けられることになっています。
完成予定は「八重洲二丁目北地区」が2022(令和4)年、「八重洲一丁目東B地区」が2025(令和7)年、「八重洲二丁目中地区」が2028(令和10)年です。これらの再開発が完成すれば、「東京」駅の交通拠点機能がさらに強化されるでしょう。
※この記事は2020(令和2)年2月に執筆されました。
第3ステージが進行する「日本橋再生計画」で世界・宇宙へ領域を広げる日本橋エリア
所在地:東京都中央区